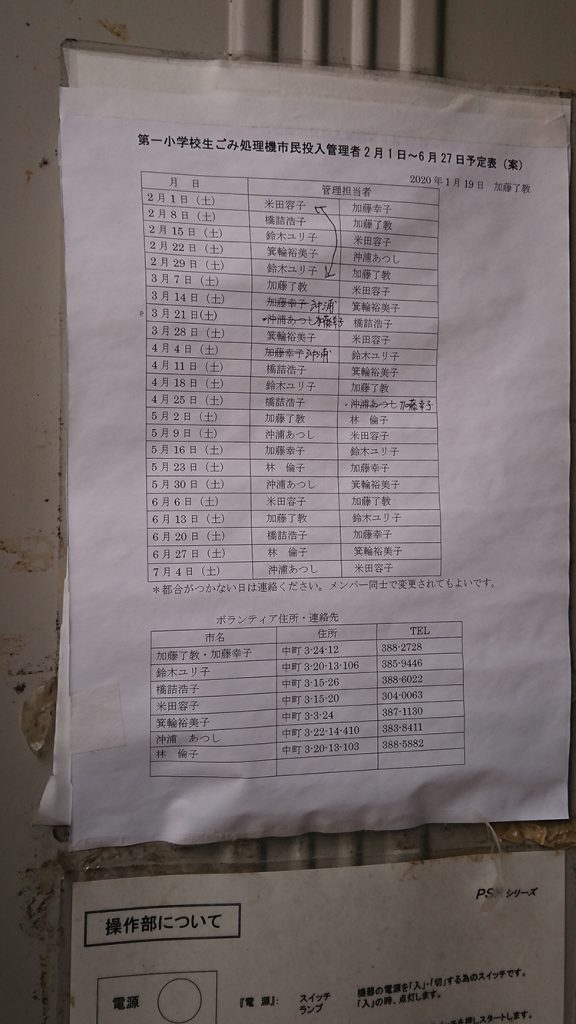第1期:情報公開が進まない理由を知る
各審議会を実際に傍聴しているとその開催予定が重なり、傍聴できない審議会が数多くあることに気が付きます。傍聴できなくても、子ども、教育、福祉などの審議会、協議会は既に傍聴者が多かったり、市民公募委員、市民活動家の方々が多く参加されているので、傍聴しなくても、市民への情報公開は進んでいるのではと安心していました。傍聴者0名という審議会を中心に傍聴していました。
それでも、情報公開(公式サイトでの会議録以外の資料の公開や関連資料が質問はされても、市議会などに市議を通じて公開されることがない)進まない審議会もあることに気づきました、一度こうした審議会を傍聴し、その理由を知りたいと思い、そうした協議会の一つ、「地域自立支援協議会(合同部会)」を傍聴してみました。以下、そのご報告です。
2020年2月21日 18:30~ 地域自立支援協議会(前原暫定施設)
幾つかある部会の合同の会議なので、十数名の方が集まります。
まず、傍聴される方の数はというと、この回では傍聴は、私と市議1名、聴覚障害者(手話サポートがつきます)1名の計3名でした。
以下、市民参加のための機能と情報公開度をご紹介します。
1)傍聴者のためにこの協議会では、「意見・提案シート」は配布されます。
2)協議会の内容の情報公開はというと、
傍聴者に対しては、
傍聴用資料は、3セット程度用意されているだけで、それ以上の傍聴者の場合は、一緒にご覧くださいとのことでした。閲覧した会議傍聴用書類(会議次第、資料1~10まで)は一切、持ち帰れませんでした。(市議は持ち帰っていたようです。この市議が一般質問でこの自立支援などの分野の質問を予定されています)
さらに、来場できない、Webなどで情報を得たいという市民に対しては、
公式サイトには会議録は公開(2月段階では、昨年の11月会議までの会議録が公開されていますが、事前の会議次第から、事後の資料などは一切、公開されていません)。同協議会の会議録は、こちらから、ご覧いただけます。
結論:情報公開は、さほど進んでいません。市民の同会議の参加者もそうしたことへの必要性を感じていないようです。「自分たちが資料を参考に活動、伝達すれば良い」、「会議で入手した資料はそいれぞれの委員が活用するのだから、それで十分」ということなのかもしれませんが、一般市民向け、傍聴者への資料提供などという点では、行政側への要請はしていません。会議録を公開しているからいいだろうという程度(どの審議会とも同様の最低限の公開度)です。
今後へ>この協議会への情報公開への要請、チャレンジをしてみます
その1:まず、「意見・提案シート」への情報公開提案をしてみます。
その2:知り合いの会議参加メンバー(委員)に協議会への情報公開推進への提案を話してみます。「会議で提案してもらう」などやそうしたことへの意見確認です。
その結果を第2弾として、後日ご紹介します!!